「うちはしあわせになってはいけんのじゃ」。
広島に投下された原子爆弾。
美津江は一命を取りとめながらも、
生き残った罪悪感を抱えて生きている。
美津江は一命を取りとめながらも、
生き残った罪悪感を抱えて生きている。
自分以外の周りの人は、皆いのちを失ったからだ。
やがて美津江は、図書館に勤め、
原爆に関する資料を集める「木下」という青年と
互いに想いを寄せ合うようになる。
しかし、その罪悪感から、
恋のときめきからも、自ら身を引こうとする。
二人を、なんとか引き合わせようと画策するのが、
美津江の父の竹造であったが、
実は竹蔵は、原爆によって命を失った幽霊なのであった・・・。

井上ひさしの『父と暮らせば』は、
戦後間もない昭和23年の広島を舞台にした、
二人芝居である。
登場人物は、美津江と父・竹造だけで、
広島弁をふんだんに盛り込んだ会話が
広島弁をふんだんに盛り込んだ会話が
物語の魅力の一つになっている。
読売演劇大賞の優秀賞をはじめ、
数多くの受賞を果たし、
フランスや香港、ロシアなどでも翻訳され、上演された。
新潮社から出されている本は、
その脚本で、セリフとト書きだけで構成されている。
この本の、文庫版の「あとがき」も、
本編に負けず劣らずおもしろい。
まず、「二人芝居」は、
本当は「一人芝居」であるという種明かし。
美津江を「いましめる娘」と「願う娘」にまずわける。
そして対立させてドラマをつくる。
しかし一人の女優さんが演じ分けるのは大変ですから、
亡くなったものたちの代表として、
彼女の父親に「願う父」を演じてもらおうと思いつきました。
べつに云えば、「娘の幸せを願う父」は、美津江のこころの中の幻なのです。
(p110,文庫版)
なるほど・・・。
他の様々な作品も、
こういう観点で読み直してみるとおもしろいかもしれない。
他の様々な作品も、
こういう観点で読み直してみるとおもしろいかもしれない。
井上ひさしは、これが小説にも詩にも真似できない、
舞台だけでのみ表現可能な、「劇場の機知」なのだと書いている。
つまり、劇場での「仕掛け」。
演出と言ってもいいかもしれない。
井上は、この「劇場の機知」こそが、
「翻訳されても失われないもの」なのだと言及する。
「翻訳されても失われないもの」なのだと言及する。
日本語で書かれた台詞は言葉の壁に突き当たり、
翻訳という名の壁壊しの作業を通して大幅にその魅力を失いますが、
劇場の機知だけは、
まったく無傷のまま言葉の壁をすんなりと通り抜けることができる。
その機知に異言語の劇場の観客がよろこぶわけです。
(p109,同)
物語のクライマックス、竹造は美津江に語りかける。
「わしの分まで生きてちょんだいよォー」。
父の娘への強い願いでありながら、
被爆者である美津江自身の悲痛な叫びでもある。
父の娘への強い願いでありながら、
被爆者である美津江自身の悲痛な叫びでもある。
この「想い」もまた、
「翻訳されても失われないもの」のひとつだと思う。
今月、オバマ大統領が広島訪問することが決まった。
アメリカの大統領が広島に来るのは、歴史上初であるらしい。
任期間際の政治家が来るだけで、
そう簡単には現状は変わらないかもしれないが、
そう簡単には現状は変わらないかもしれないが、
実際に色々のものを目にして、話を聞く中で、
「翻訳されても失われないもの」の力が、
少しでも世界を良い方向に後押ししてくれることを
願いたいと思う。
少しでも世界を良い方向に後押ししてくれることを
願いたいと思う。
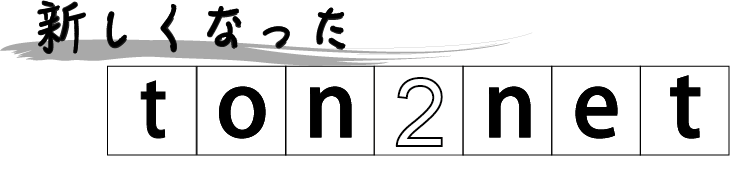



コメント