気づけば、はや2月になってしまった…。(ことしもよろしくお願いします。)
年末年始を思い起こしてみると、引き続き、古民家で肉体労働。
土の入った土嚢袋やら、湯たんぽより大きい石などを一輪車でよろよろ運んだり。
きっと、よい家ができるはずであります…。
ただ、工務店さんからは「お引越しに…間に合わせたい…と思ってはおります…」という若干な弱気発言。確かに、床下開けてみたら、傷みが想定よりも激しかったので仕方ないところもあるのだが…。
どうなることやら。
古民家に行かない日には、サーモン燻製したり、久々に本を整理したり(引越しに備えて)。

こういう作業のお供にラジオをよく聞くようになった。
radikoで聞くものがなくなると、落語を聞いたりもする。
年の暮れ・明けになると聞きたくなる演目ってありますよね。
たとえば年末にはやっぱり「芝浜」を聞くとほっこりする。
大晦日にお風呂に入ると、「歳の暮れに、誰も彼もサッパリしたいっていう気持ちはおんなじだ」という一節を思いだす。ほんと、そうだね。
お正月なら、初天神とか。あとは、最近知った「黄金(きん)の大黒」なんかも、縁起がよくていいですね。
これらに加えて、ふとしたことで、今年は「千両蜜柑(せんりょうみかん)」が聞きたくなった。

実は奥さんが大のみかん好きで、「あ〜、みかんが一年中食べられたらいいのにな」という発言をして、「なんか、そんな話あったな…あ、『千両蜜柑』」と、思い出したのだった。
千両蜜柑は、ある大店(おおだな)の若旦那が「夏だけど蜜柑食べたい…」といって床に伏してしまう。江戸一の名医にも「悩みを解決するしか治す方法はない」と言われ、お店の番頭さんが江戸中を探して、たったひとつだけれども、みかんを見つけてくる…という筋のお話しである。
筋を簡単に書くと、「なんだ。」という話である。
でも、「もしこういうことがあったら」という仮定から始まって、市井の人が「どうなるのか」というシミュレーションが生き生きとしていて、つい、聞いてしまう。
番頭さんは蜜柑丼屋にたどりつき、冬の間から蔵いっぱい保存してあったみかんの中で、ひとつだけ、無事なものがみつかり、安堵する(見つからなかったら、店の主人に殺されると言われている)。
問屋の主人から「1個千両」と破格の値段を提示されるも、店の主人は「安い」と即金で一括購入する。床に伏していた若旦那は、そのみかんをうまいうまいと食べて礼を言う。「両親とお前に、お礼だ」といってみかん10袋(房というか)中の残りの3袋を番頭さんに渡す。
番頭さんは、主人からのれん分けをしてお店を持つ予定になっているらしいのだが、そのときに貰える金もたかだか50両程度。いま、手元に300両相当のみかんがある…といって行方をくらましてしまう…というサゲだ。
番頭は、なぜ、のれんわけの権利を捨ててどこかに行ってしまうのか。みかん3房を300両相当と勘違いして、両親に渡すはずの2房も「持ち逃げ」した…という捉え方もあるかもしれないが、違うのではないかと思う。
自分がこれまでの生涯、コツコツと働いて得たのれんわけの権利が50両。しかし、いま手の中にある3房のみかんが300両。「お金」「価値」というものが、番頭さんの中でゆらぎ、混乱し、すべてがバカらしくなってしまったのかもしれない。このあと、番頭さんはどんな人生を送るのだろうかと、考えずにはいられない話である。
落語のオチには、間抜けで笑えるもの(間抜けオチ)や、ダジャレ(地口オチ)や、決め台詞(とたんオチ)などいろいろな種類があるが、こう言った「なるほどねえ…」としみじみ考えさせられる終わり方も、あるのである。
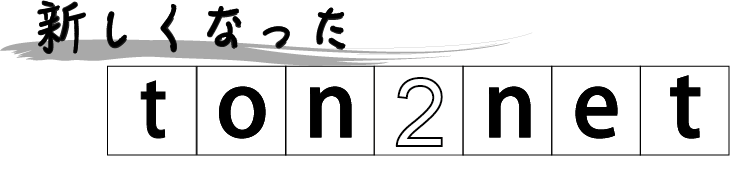



コメント