…はっ!
気づけば前の更新から1ヶ月…。
いよいよ引越して住み始めたり入学式があったり、いろいろありました…。
前回、竹小舞まで書きました。
きょうはその続き。土壁を塗っていきます。

まず、壁用の土をつくります。
荒木田土という田んぼの土の中に細かく切った藁を入れ、水と混ぜます。
荒木田土は、もともと、関東の荒川沿いにある土地の「水田の底に溜まった土」のことらしいのですが、最近は荒川沿いじゃなくてもそう呼ぶそうです。粘土が高く、固まりやすい。暗褐色で艶があって見た目もよろしく加工に最適らしい。国技館の土俵にも使われているらしいですよ。
これが荒木田土。

えっほ、えっほ、とバケツに入れて、藁のはいったクソデカ容器に投入していきます。
妻と話しているのですが、最近、縁の下の土を掘って運び出したりと、土を運んでばかりいるな…と。地下強制労働所でやっている作業ってこんな感じの過酷バージョンなのかもしれない。寝る前に地獄チンチロでも始めるかぁ。
藁。ここに投入していきます。

で、土・藁・水をうおおおおおおおと攪拌するのですが、ここで!我が家が縁の下の土をやわらかくするために買ったハンディー耕運機くん(中古)が大活躍!きょうから君は幸運機だ。

大工さんも「これはいいですね…一台買おうかな」とおっしゃってました。
下は、大工さんたちが3人がかりでおらおらあと練っている様子です。土は混ぜるのも運ぶのも大変。

完成した土はこんな感じ。泥!
ところどころ、藁がみえています。

この泥を「コテ」で、どんどん塗っていきます!

まず外。で数日乾かして内側からも塗ります。
土をコテにつけて、パンチするようにどんっとおしつけて、竹の間からむにゅっと出るようにします。そうすると落ちません。竹に乗せてから、広げるとよいそうです。
右利きの場合、左上から初めて、外に力をかけるように右に伸ばしていきます。
これが「左官」の語源だとかそうじゃないとか…と左官屋さんがおっしゃっていました。
あと、左官屋さんがおっしゃっていた言葉メモ
- 体が痛くなってからがスタート
- きれいにぬりたければ道具をきれいにしておくこと
- 特にはしっこなどをコテの先で整えると、一見、きれいに見えるが全体で見ると全然でこぼこだったりする。これが「小手先」。
学びが深いです。
たしかに土塗りは体力勝負感があって、道具がきれいでなく土がついていると、常に無駄な重りがついているようになってすぐに疲れてしまいます。
あと土の中の水が多すぎるとべちょべちょで落ちやすいし、少なすぎても硬くて塗るのがめっちゃ大変です。
慣れない筋肉をつかって腰・肩・腕と右手の薬指と小指がめっちゃいたい、ここ最近の毎朝です。
ただ、少しずつ外界と中を仕切る壁ができていく実感は、「家づくり」のひとつの醍醐味でもありましょう。たぶん。.

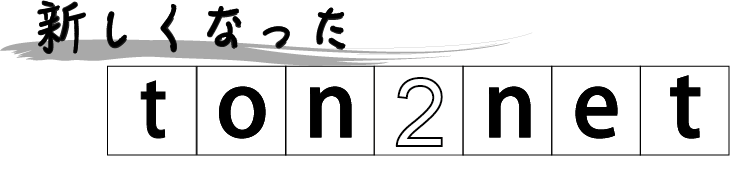




コメント