かなり経ってしまったのだが、
アニメ監督の高畑勲(たかはた・いさお)さんが
お亡くなりになった。
追悼企画としてテレビ放映された
「火垂るの墓」を、10何年かぶりに見た。
子ども時代に一度見て、あまりにも怖くて、つらくて、
また見直すことが、できないでいたのだった。
(以下、映画『火垂るの墓』について書いていきますが、
もし見てない人がいたら、
こんなブログは読まなくていいので(超絶、ネタばれですし)
ぜひ、映画を見てください。本当におススメです。)
さて、大人になって改めて見てみると、
本当に様々な発見のある映画だった。
一番大きかったと思ったのは、
子ども時代に強烈に思った、
「このババア…。ぜってぇー、ゆるせねー…。」
という点。
戦時中、主人公と妹(節子)は、空襲で身寄りを亡くす。
仕方なく、知り合いのおばさんの家に疎開し、
難を逃れようとする。
おばさんは、最初こそ、愛想よく迎えてくれるのだが、
戦況は悪くなり、食料事情も日に日に悪化。
主人公と妹に対して、段々と冷たい態度をとるようになる。
主人公が、母の形見の着物と交換に手に入れた米も、
大部分をおばさんがあずかることに。
おかゆをよそうとき、二人には米はちょっとしか与えず、
自分の家族(夫、娘、息子)にはしっかりよそうなど、
目に見えて「居候に迷惑している」というような態度をとるようになるのだ。
このシーンをよーく見ると、おばさんの娘はこの状況に気づき、
羞恥心からなのか、一瞬だけ顔を赤らめる演出がなされている。

時間にして1秒に満たないくらいのカットなのだが、
高畑さんの演出への細かい気配りが、垣間見えるシーンだ。
この後、兄妹は家を出て
防空壕での二人暮らしを始めることになる。この場面を改めてみて思ったのは、
なんというか、このおばさん、「普通の人」だったのか…
という「怖さ」だった。
子ども時代の自分は、このおばさんを
「異常に冷酷な人」と思ってみていた。
でも、高畑さんはそうは思っていないだろうし、
実際、そうじゃないだろうと思う。
つまり、こういうことだ。
同じ状況だったら、自分も、同じことをするかもな、ということなのだ。
このおばさんも、食べ物のたくわえが乏しくなかったら、
戦争じゃなかったら、
別にこんなことはしなかっただろうと思う。
「普通の人」が、こういう状況になったら…という、
ある種の「シミュレーション」なんだと思った。
子どものころに抱いた「異常で怖い」という印象。
でも、実は「普通」を描いているからこそ、
もっともっと心の底が冷えるような怖いシーンになっているし、
「戦争」という一面を、具体的に描くことに成功しているのだと思った。
もう一つ、びっくりしたのが、
そもそものこの作品の「構造」。
実はこの映画、主人公の亡霊が、
妹と自分のいきさつを、
時空を移動して見届ける…という構造なのだった。
(回想ではない。兄の亡霊が改めて痛々しい状況を見届ける映画なのだ。)
それを意識しながらみると、
本当にもう子どものころとは違う意味で、
”泣ける”映画だなあ…と思ってしまったのだが、
ここで、高畑さんは言うのだ。
泣いてなんか欲しくない、と。
その意味を知ったのは、
TBSラジオの「セッション22」という番組の高畑さんの追悼特集 だった。
「この世界の片隅に」の監督であり、高畑さんとともに仕事をしてきたという片淵須直さんがゲストだった。
(リンクから全部聞けるので、興味ある方はぜひ聞いてみて欲しいです。)
片淵さんによれば、ある日、高畑さんを取材に来た記者が
「ファンなんです(にっこり)」と言うと、高畑さんは
「ファンに用は無い」と追い返したという(!)。
一見、偏屈なおじさんのようにも思えるこのエピソードなのだが、
実は、高畑さんには、自分の作品を見る時に、
視聴者に求めることがあったのだという話が続く。
「火垂るの墓」を見たスタッフが、高畑さんに
「泣けました」と感想を言うと、高畑さんは怒ったらしい。
「泣いてる場合じゃない」と。
泣いたら、「かわいそう」で思考は終わってしまう。
泣いてないで、もっと、その先まで考えながら見てほしいんだと。
高畑さんは、制作者にはもちろん、
片淵さんは語っている。

カットが切り替わり、兄がみつめていたものが画面に映し出される。

戦争を忘れた、現代の都市。もうこの時点で、
「そ、そんな映画だったのか…」と衝撃を受けたのだが、
もう一度、カットが変わる。

さっきと同じカットのようにも思えるが、
兄の視線の方向が、よく見ると少し変わっているのがわかる。
きっとどちらも、泣いている場合じゃないよと、
「その先」を考えるよう促しているのだと思う。
高畑さんは、制作者にはことさら厳しいレベルを要求した。
その一つが、「主人公と同じレベルにいたらダメだ」ということだったという。
泣きそうな主人公を描くとき、むしろ笑えるように描いてみる。
そういう「客観視」によって、
見る人に伝わる何かがあるはずだと信じていたのではないかという。
高畑さんと現場をともにした、
監督の片淵さん。
特集番組のラストを、こう締めくくっていた。
「僕は一生懸命、”笑える戦争映画”として『この世界の片隅に』を作って、
そしたら、高畑さんは最後に
『エールを送ります。』って…
その言葉は、直接聞けなかったんです。
人づてに…エールを送りますって伝えてくれって言われて。
それが僕が高畑さんからもらった、最後の言葉ですね。」
2018年4月13日「金曜ロードSHOW!」(日本テレビ)放送回をテレビ画面接写。
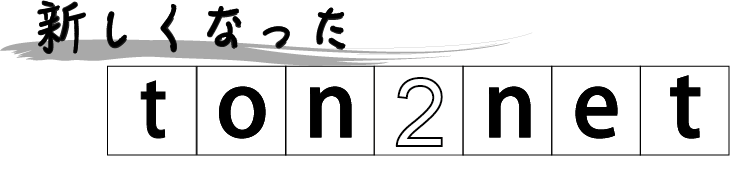



コメント