「そうして何もしないでいていいの。」
という母親の問いに、中学生の「わたし」は答えるわけにはいかない。
いいと言えば「いい訳ないでしょ。」と来るし、
よくないと言えば、「分かっているのに、なぜ。」
と返されてしまうからだ。
部屋のハンガーにも、私の気持ちにもごわりとしてなじまない
真新しい制服を部屋にかけて、
「わたし」は、テレビゲームのスイッチを入れる。
「魔の山」を越えるアイテムがどうしてもみつからず、
ジャンプをし損なって谷底に消えた「わたし」に
母親から声がかかる。
「おじいちゃんの具合、よくないらしいのよ。
すぐ行くから、支度しなさい。」

安東みきえは、山梨県生まれの児童文学作家。
この「そこまで とべたら」は、教科書のための書き下ろし小説だ。
中学校で出会う最初の小説にふさわしい、メッセージ性のある良い小説だと思う。
「わたし」は、病室でおじいちゃんに面会するが、
おじいちゃんは意識が混乱しているのか、「わたし」が「わたし」だとわからない。
おじいちゃんは、「わたし」に向かって「わたし」の自慢話をする。
あんた、知ってはりましたかなぁ。
わたしの孫娘がね、県大会の幅跳びで一等賞もろたんですわ。
えらいもんでっしゃろ。
「わたし」はおじいちゃんに悟られないように涙を払う。
やっと顔をあげると、「あんた」になりすまして、わたしは言った。
「その孫むすめって人が、わたしに教えてくれたよ。
おじいさんのこと、大好きだって。」
じいちゃんはうれしそうに笑った。
じいちゃんうそじゃないよ。
わたしの何がうそでも、これだけはうそじゃないよ。
明け方近くに、私はそっとじいちゃんの病室をのぞいてから、
一階へ降りて庭へ出る。
靴の先で足下へ線を引きながら、「わたし」は思う。
目標は桜の木。
そこまでとべたら、じいちゃんは治る。
空がだんだん明るくなって、夜がどんどん逃げて行く。
「わたし」は、県大会の前にじいちゃんが
内緒で靴を買ってくれたエピソードを思い出しながら、助走に入る。
父さんと母さんは、県大会にはいつもの慣れた靴でいいと言った。
でもわたしは、もっと軽い靴が欲しかった。
そしたら、じいちゃんが内緒で靴を買ってくれた。自分がいいと思うことをやれって。
それが、いちばんのおまじないだって。
助走を終えた「わたし」は、軽々と空へ舞い上がる。
その後、一命をとりとめたじいちゃんに「わたし」は声をかける。
じいちゃん、わたし、決めたの。
陸上部、入ってみるよ。
そして物語は結びへ。
なんにもしないじいちゃんだから、仕事もたくさんはしなかった。
老人会にも入らなかった。
戦争へ行っても戦わなかった。
そして今度は、自分が死ぬこともしなかった。でもじいちゃんは、わたしに靴を買ってくれた。
じいちゃんのしないこと、じいちゃんのすること。
わたしには、わかったような気がする。わたしも、今度は自分で決めるよ。
中学校の時、退屈な授業中はいつも国語の教科書を読んでいた。
この話も、本当に何回も何回も繰り返し読んだ。
大学に入って一人暮らしを始める際にも、この教科書は手放さずに持ってきた。
繰り返し、繰り返し読んだり聞いたりした小説や音楽に
少し時間をおいてまた触れてみると、
また新しい良さが見えてくる。
何を選んで、何を選ばないのか。
選ぶことを恐れて、ともすれば様々な要因に流されがちになる。
そうして、後になってから不安になったり、不満を口にしたりしてしまう。
しかし、この物語の中で、じいちゃんは
「つまらん思うことはやめときや。」
と「わたし」にアドバイスする。
選択をするのは自分自身でなければならないのだ、というメッセージを送る。
そして、その選択の最も優れた指針、おまじないは、
「自分が良いと思うことをすること」
なのだと語りかける。
何かを選ぶことは、他の何かを選ばないということでもある。
でも、そこから目をそらして、自分の人生を生きることはできないのかもしれない。
私たちにできるのは、自分の選択に自信と覚悟を持つこと。
そして、選択の指針である「自分が良いと思うこと」に対する感覚を磨くことだ。
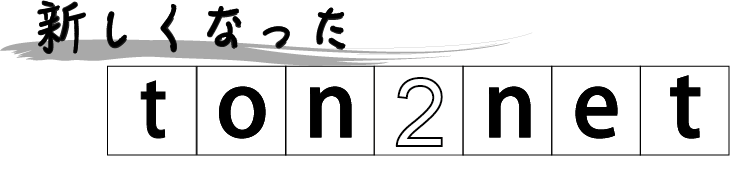



コメント