国立科学博物館で行われている集中講義で、
「私にとっての博物館」という課題エッセイが出されました。
人気投票の結果、24作品中の栄えある一位に選んでいただいたので、
ここに自慢の意味を込めて掲載します。
(なぜか、全作品・名前非公表で、誰もほめてくれないんですよ…。)
ちょっと長いですけど、どうぞ。
亡くなった祖父の形見として、私は一つの石を持っている。
上品な青をたたえた銀色の光沢を放つこの石を見ると、私はいつも祖父を、
そして祖父が自宅のはなれに作った”石の博物館”を思い出してしまうのだ。
初めてそこに入ったのは、小学生の夏だったと思う。
夏の日差しや、蝉の鳴き声の激しい屋外とは対照的に、
その部屋は暗くひんやりとしていて、なぜなのか驚くくらいに静かだった。
「石集め」が趣味だった祖父は、その部屋に実に様々な石をコレクションしていた。
水晶のように透明できらきら輝くものや、エメラルドのようなはっとする緑のもの。
木がそのまま固まったような珍しい石も有った。
その部屋に入った私や兄や妹は、見た事の無い石の数々に驚き、魅了された。
手に取り裏返したり、撫でたりした。
そんな姿を、祖父は部屋の片隅から終始にこにこと見守っていた。
そんな祖父が亡くなったのは、私が大学に進んでからだった。
寮の部屋で訃報の電話を受け取った私は、
翌日のお葬式の時間を確認して電話を切った。
窓の外からは、気の早い秋の虫の声がしたのを覚えている。
ふと、あれはどこにしまったろうと思って、祖父の形見の石を探した。
引き出しの中にそれはあった。
最後に祖父に会ったのは病院のベッドの上だった。
別れ際、陽気な祖父が肩を震わせていたのが忘れられない。
でも、その石が私に思い出させたのは、まだ元気だった頃の、
”石の博物館”の館長である祖父だった。
にこにこして、いつも冗談ばかり言っていた祖父は、本当に石が好きだった。
私は、祖父から石の名前やそれを集めた経緯などの解説を聞いたことは無い。
(今となってはなぜ質問しなかったのかが不思議なくらいなのだが。)
けれども、祖父の石を眺める優しい目。
新しく仕入れた石の台を自作する時の真剣なまなざし。
そして、コレクションの中のいくつかを
私たちに手渡してくれるときの嬉しそうな表情が、
具体的な「説明に勝る何か」を語っていたように思う。
博物館には、形あるものが展示される。
当然、言葉による説明が添えられるものだ。
けれども私が思うに、良い博物館は展示された何かを通して、
言葉で表せない大きな「何か」を、
来館した人々の心の中に残すことができるものではないかと思うのだ。
祖父の”石の博物館”のひんやりとした空気や、石に囲まれた空間の独特な雰囲気。
そして何より、そこにいた祖父を私はありありと思い出すことができる。
展示物の名前なんか、内容なんか覚えてなくたっていい、と私は思ってしまう。
画面の向こうや写真に見るのではなく、実物として並ぶたくさんの展示品。
それらに囲まれることによって生まれる独特の空気。
館内のざわめき。
そういうものが、知らず知らず、少しずつ、心の中で私たちの一部に成ってゆく。
私にとっての博物館は、そういうものだ。
今になってみて思う。
祖父の博物館が、今の私の一部を作っているのだと。
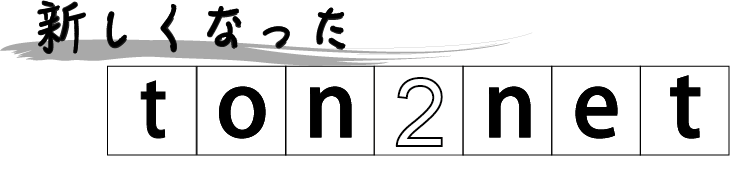


コメント